富士通が2020年から進めている全社DXプロジェクト”フジトラ”。プロジェクトの重要テーマの1つであるデータドリブン経営を実現するにあたって重要な役割を果たすのが、データアナリティクスセンター(DAC)だ。DACを率いるのは池田栄次氏(CEO室 DAC センター長)。4年が経過した現在、データ活用の成功法則を見出しつつある。
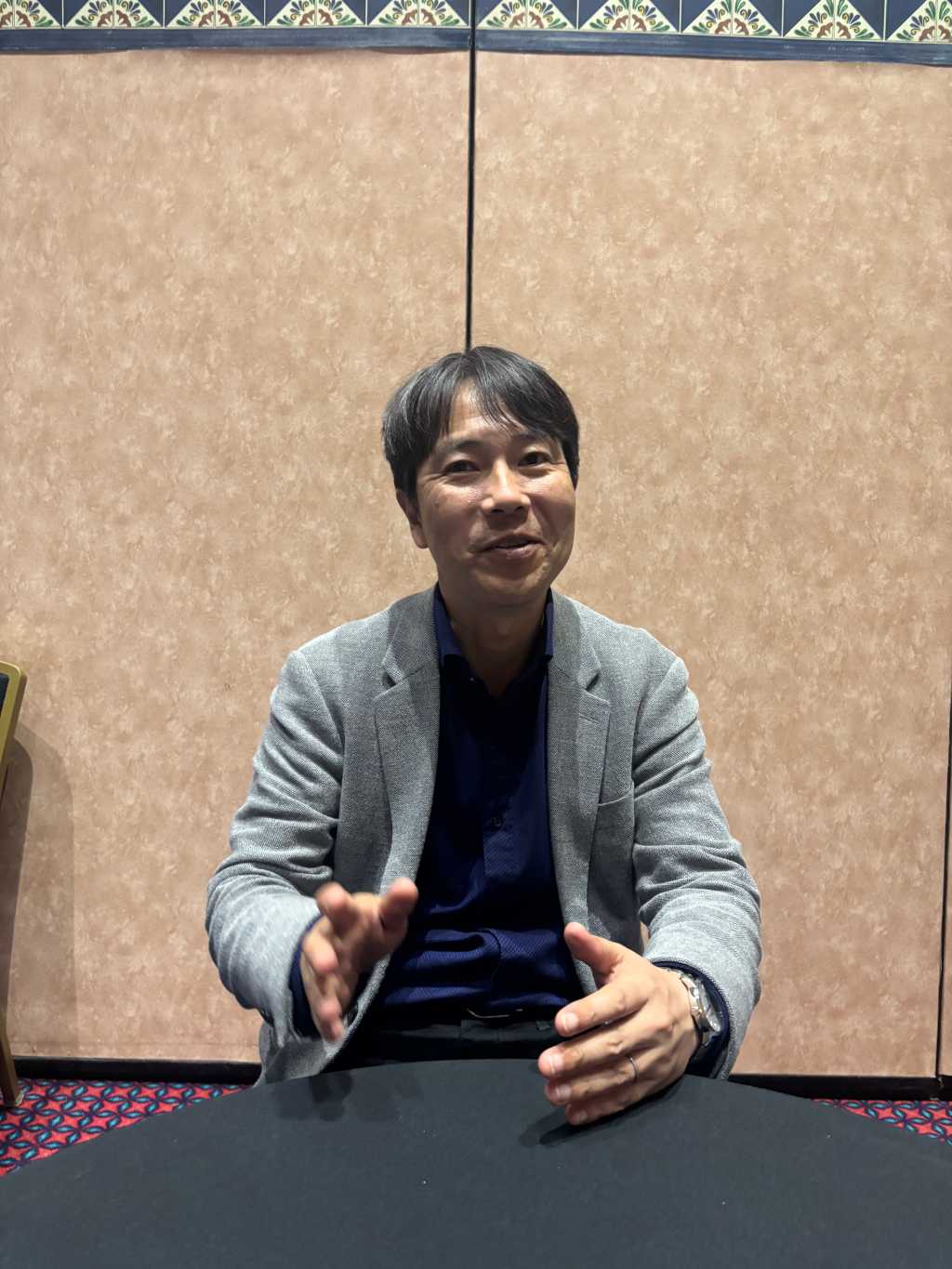
データはある、だがどうやって価値を出すのか?ーー解は”クイックウィン”
いかなる組織においても変革は簡単ではない。12万4000人の大所帯となるとなおさらだ。だが変革なしに生き残れないーーそんな思いで富士通は2020年、全社DXプロジェクトに乗り出した。題して「フジトラ」。Fujitsu Transformationの略だ。
フジトラはさまざまなプログラムを含む壮大な経営プロジェクトで、その中にはOneFujitsuプログラムがある。これを紐解くと、OneDataとしてデータ環境の標準化、OneERP+として全世界でERPの標準化、OneCRMとして全世界でCRMの標準化などが含まれている。
目指すのは、データドリブン経営と業務効率化。データドリブンな組織になることで事業変革に即応できる未来予測型経営を実現する。業務効率化の先にあるのは高付加価値業務へのシフトだ。
DACはフジトラが始動した翌年に立ち上がった。ミッションは、グローバル標準化戦略の下で全社データドリブン経営を推進すること。CEO室に属し、データ活用環境整備、各組織のDX推進といったデータ活用の取り組みに加え、組織横断のデータコミュニティの創出、全社を巻き込むような施策の展開なども担っている。
立ち上げ当初から試行錯誤の連続だった。「暗中模索の状態で失敗もたくさんあった。その中から小さな成功を重ねてきた」と池田氏は明かす。取り組みの甲斐あって、データの活用は進んでいる。2023年3月と比較すると、OneDataの利用者は2万7000人から8万4000人に、利用部門数は140部門から380部門に、ダッシュボードの数は250から680に増えた。
スタート当時を振り返り、池田氏は「最初は成果を小さく出す”クイックウィン”が大事」と話す。「データは手元にあるが、どうやってデータから価値を出すのかがわからず、止まってしまうことが多い」からだ。小さな成功を重ねることで、少しずつサイクルが回りだす。
クイックウィンから見えてきた成功のための5要素
このように、クイックウィンはフジトラ開始直後の1〜2年間におけるスタートダッシュの中核を担った。技術面では、データの統合・分析技術を提供するPalantir Technologiesと提携し、プロジェクト単位でPalantirを活用した。最初に効果を実証したのが財務経理部門だった。
それまで財務経理は各部門から送られてくるExcelの集計をもとに財務データを提供していた。しかし、「なぜこの部門の売り上げが落ちたのか」「なぜこの部門が急成長したのか」と言った質問に即座に答えることが難しかった。詳細な分析をすることで、そのような質問に答えられるようにしたいという強いニーズがあった。その結果、すべてが実現したわけではないが、データを手に質問に対応できる環境を作った。
成功のポイントは「業務側である財務経理本部が一緒に取り組んだこと」と池田氏は断言する。
このようなクイックウィンをいくつか重ねるうちに、成功のパターンが見えてきたという。「必要条件として5つが揃う必要がある。業務部門のリーダーシップ、DACのようなテクノロジーを扱うチーム、データ、オーナーシップ(経営層の関与)、アジャイル」と5つをあげる。オーナーシップは財務経理プロジェクトの場合はCFOがとった。「経営層が強く関与し続ける。現場だけで頑張るというパターンはどこかで止まってしまう」。
クイックウィンを通じて”勝ちパターン”が見えてきた段階を、池田氏は「練習期間」と位置付ける。「データの加工や組み合わせ、分析方法、視覚化の方法などは、練習しないとわからない。それを実際の具体的な課題を解きながら、我々も学ぶことができた」。
ちょうど同じ頃、並行して進めていたOneData環境とOneCRMが整った。これにより、データ活用は重要な転換点を迎える。キーワードは「フラッグシッププロジェクト」だ。
フラッグシッププロジェクトで全社インパクトを実現
クイックウィンが実践的で現場レベルとすれば、フラッグシッププロジェクトは経営プロジェクト。”TIGERプロジェクト”という別称をもつ。ここでは、完成したOneCRMのデータを使いこなすことを掲げ、毎週のように経営層とDACそして現場リーダーがデータの使い方、活用を考えた。その期間は約2年に及んだ。
その1つの成果が、CRMにある受注データからパイプラインを見て受注を予測する仕組みだ。「それまでのダッシュボードは現状把握にとどまっていたが、将来が予測できるようになった」と池田氏、これにより組織に変化が生まれた。目標に到達しないとわかった社員は、データを見ながら必要な打ち手や施策を打つようになったのだーーデータ活用のサイクルができていった。データドリブン経営の目標に掲げる未来予測型経営の第一歩だ。
成功ばかりではない。リクエストに対してダッシュボードの改良が追いつかない、ダッシュボードが使われない、データ標準化の過渡期であるためシングルソース化の担保が難しい、などの課題に直面した。
成功の5条件が揃わなかったプロジェクトもあった。あるプロジェクトでは海外のデータを使う必要があったが、データの域外移転は規制などの問題があり複雑だ。「3ヶ月、半年待ってもデータを持ってくることができず、頓挫した」と振り返る。また、経営層の関与がないケースでは、「業務側のリーダーシップがあり、データもあり、我々も支援した。だが、推進力がなくなり、リソースの投入もなくなり、最終的に止まってしまった」という。
このような経験から、DACは3年目になると5条件が揃っているプロジェクトを優先するアプローチに変えた。
このように、クイックウィンが「部門単位にインパクトがある実践的な学びの蓄積期間」だったのに対し、OneDataを使ったフラッグシッププロジェクトの展開は「全社にインパクトをもたらす成功事例創出のメカニズムを習得した期間」と池田氏は位置付ける。
データ活用支援は技術と人の両輪
ここで組織としてのDACを見てみよう。DACは数人でスタートし、拡充していった。メンバーはさまざまな部門から加わっており、技術者だけでなくデザイナーなど多様な人材がいる。
技術面での成果を示すものとして、DACが作成したダッシュボードは2022年末に5種、23年末には20種に増えた。このような技術支援に加えて、池田氏が当初からこだわっていたのが”データプラクティス”と呼ばれる、人の意識や行動を変える取り組みだ。
例えば個人が挑戦するデータ分析コンペは2022年度の応募者は98人、2024年度は674人(そのうち、59人が社外)。組織の成熟度を評価するプログラム、アワード、経営シミュレーション体感プログラムなども展開している。
「データの技術的支援と行動や意識を変える取り組み。この両輪で進めなければ、データドリブンは成功しないと考えた」と説明する。
このような取り組みを進める中で、池田氏は重要な気づきを得た。「当初は”全社12.4万人にデータドリブン経営を浸透させる”という目標を掲げていたが、そう単純ではないのでは」というものだ。どういう意味なのか?
「リーダーは、自分たちのビジネスが正しい方向に向かっているかを見なければならない。一方、ダッシュボードを俯瞰的に見るよりも、自分の持ち場でしっかりとデータを入れる役目を果たす人もいる」。全員が画一的にデータドリブンではなく、立場によって比重が異なるという考えに至ったのだ。
このように、DAC立ち上げから4年間、池田氏は走りながら軌道修正をしていった。
第2ラウンドへーーAI時代のデータドリブン経営
現在、DACの取り組みは新たなフェーズに入っている。池田氏が「第2ラウンド」と表現するこの段階では、AI技術の本格導入が始まっている。
取り組みの1つとして、AIエージェントによる意思決定支援などのプロジェクトが進んでいる。生成AIのエンジンやAIエージェントは自社技術と社外技術の組み合わせで用途に合わせて実装している。経営層自らが率先して使っており、経営会議でも実践を積み重ねているという。
幸い、これまでのデータの取り組みを通じてデータはかなり整備されている。「AIもデータも使わないとだめ。使ってどんどん磨き上げることで、役に立つツールになる」と池田氏。データが”AIレディ”になってきたことで、AIによる予測も始まっている。「すでに誤差は1ケタ%のレベル」まで向上している。
今後1-2年で、Excelでの集計から、AIを使った予測に切り替える予定だ。これにより、営業なら顧客に向き合うなど本来費やすべきところに時間を費やすことができるとみる。
また、OneFujitsuの難関であるOneERP+が、いよいよ2024年秋に始まった。日本からスタートし、APACやその他の海外拠点が合流する予定だ。基幹システムであるSAPのデータが統合されることで、これまで以上にデータ活用の幅と深さが広がる。「もう一段深くデータを浸透させるフェーズに来た。組織単位でがっつりと根づかせる段階」と池田氏。ここでは全員が同じ共通理解のもとでビジネスを進める必要があるため、トップダウンアプローチがさらに重要になる、と池田氏。
財務データ、人事データ、調達データなど、あらゆる企業活動のデータが一元化され、真の意味での全社データドリブン経営が実現に近づいている。「これから1-2年で、いよいよ本当にデジタライズ、モダナイズしていく。まずそれを確実にやり遂げたい」。
第2ラウンドとして、DACは2つの戦略を進めている。1つ目はOneDataとAIを使う標準化されたデータ活用サービスの拡充、2つ目は、そうした標準サービスを前提とした経営・現場でのマネジメントモデルの変革だ。各部門のスキル取得の支援も引き続き重要だ。部門が自らデータの課題を解決できることを目指すが、ツールの統一は徹底している。「データはOneData、BIツールはQlikSense。BIツールが複数あると、全てのスキル習得が必要になり、コスト負担が大きい」と話す。
これまでの取り組みを振り返りながら、池田氏は実感と共に「変革は10年の計」と語る。
「進化をし続けないと我々の存在価値はない。それはDACのメンバーに言い聞かせている。ダッシュボードやアプローチ方法が変化してなかったら、それは赤色信号。変わっていないことが最大の問題でありリスクだ」。
12万4000人という巨大組織の変革に向けた池田氏の挑戦は、今日も続いている。








