今回、「Leadership Live Japan」に出演するゲスト、株式会社荏原製作所の執行役 CIO(情報通信担当)の小和瀬浩之氏をお迎えし、CIOのキャリアや仕事観、やりがい、魅力などについて語ってもらいました。
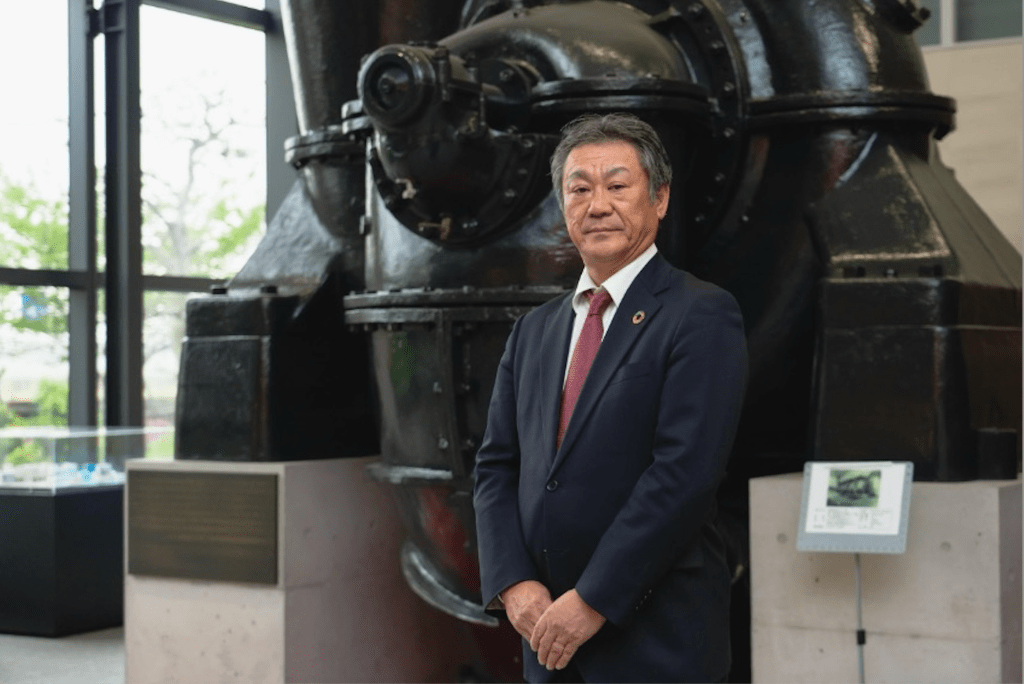
「ITは現場から変える」〜ユーザー企業出身CIOのリアル〜
私は大学卒業後、花王に入社。日本を代表する消費財メーカーで、27年間にわたりIT部門を中心にキャリアを積み重ねました。システム部門の統括として、いわば“現場に根ざしたCIO”の役割を担い、企業のIT戦略と現場の橋渡しを実践してきました。
その後、LIXILにてCIOとしての経験をさらに深め、現在は荏原製作所でCIOを務めています。特筆すべきは、ITベンダーやコンサル出身ではなく、ユーザー企業の中で10年以上にわたりCIOを務めてきたという点です。現場感覚と経営視点を兼ね備えた、実践型のITリーダーとして、企業のDX推進に貢献し続けています。
ERP導入による見える化で業績を変えた:SAPと歩んだ30年の軌跡
1995年、花王での海外駐在中に、初めてERP(エンタープライズ・リソース・プランニング/統合基幹業務システム:SAP)を導入したことが、私のキャリアの大きな転機となりました。業務の「見える化」を進めたことで、現地法人の業績は劇的に改善。その成功体験を皮切りに、アジア、欧米、そして日本へとSAP導入を展開し、グローバル全体での業務標準化と業績向上を実現してきました。
この30年近く、SAPを通じて一貫して取り組んできたのは、単なるシステム導入ではなく、「業務の変革」と「カルチャーの変革」です。特に印象的だったのは、アメリカでの導入時。単位の違い(ポンド vs キログラム)という些細に見える違いが、現場にとっては大きな壁になります。そんな時、私は現場に足を運び、「困っていることを教えてほしい」と対話を重ね、課題を一緒に解決することで信頼を築いてきました。
日本企業とグローバル企業では、SAP導入の目的が根本的に異なります。グローバル企業では、SAP導入=業務標準化・グローバル一体運営の手段。一方、日本企業では、導入自体が目的化しがちです。
だからこそ、私は「チェンジマネジメント」の重要性を強く感じています。
特に大切なのは、E&C(Education & Communication)。プロジェクト初期から、なぜこの変革が必要なのかを、現場の社員一人ひとりに丁寧に伝え続けること。20年、30年と同じ業務を続けてきた人にとって、やり方を変えるのは命がけの挑戦です。だからこそ、押し付けるのではなく、共に考え、共に進む姿勢が不可欠なのです。
“見える化”の先にあるもの:ERPが導いたグローバル経営改革
「ERPとは単なるシステムではなく、経営の概念である」
これは私が長年の経験から確信していることです。ERPは、企業の経営資源を“全体最適”で活用するための考え方であり、それを具現化したのがSAPのような統合基幹業務システムです。
私が初めてSAPを導入したのは1995年、花王での海外駐在時でした。当時は販売、生産、会計などがバラバラに管理されていた時代。ERPの導入によって、業務がリアルタイムで連携され、業務の“見える化”が一気に進みました。
しかし、ERPは単にシステムを入れれば済むものではありません。販売、物流、生産、購買、会計といった基幹業務のレベルを一定以上に引き上げなければ、導入は成功しません。つまり、ERP導入とは業務の底上げであり、企業文化の変革でもあるのです。
現在私がCIOを務める荏原製作所でも、SAP導入は「経営改革」の一環として位置づけています。目的はグローバル経営の実現。そのために、17カ国以上で業務標準化を進め、属人化された業務をプロセスとして定義し直し、全社的な業務レベルの向上に取り組んでいます。
しかし、このプロセスは決して容易ではありません。特に日本企業では、システム導入が目的化しがちで、業務改革やカルチャー変革が後回しになりがちです。だからこそ、私は常に「なぜこれをやるのか」を現場に伝え続け、業務の本質に向き合いながら、経営そのものを変えていくことを大切にしてきました。
受け身のITから、攻めのITへ:海外駐在で180度変わった視点と全体最適の力
私のキャリアは、花王のシステム開発部から始まりました。国内外でIT担当として経験を積む中で、特に若い頃は「ユーザー部門から言われたことをシステム化するのが仕事」だと考えていました。いわば“受け身”の姿勢です。
しかし、海外駐在を経験したことで、その考え方は180度変わりました。海外では、業務側も何をどう改善すべきか分からないというケースが多く、IT部門が自ら経営や業務の課題を見つけ、システムという手段で解決していく必要がありました。ITは受け身ではなく、経営のパートナーとして“攻め”の姿勢が求められる──そう強く実感したのです。
日本企業では、業務部門が一つの部署に長く留まり、部分最適の視点に偏りがちです。一方で、IT部門は全社を横断する立場にあり、“鳥の目”で全体を俯瞰し、“虫の目”で細部のロジックにも対応するという、両方の視点を持つことができます。
だからこそ、IT部門こそが全体最適をリードすべき存在にならなければなりません。業務の現場に寄り添いながらも、他社の事例や業界の動向を学び、積極的に提案していく姿勢が不可欠です。私自身、そうした姿勢を貫くことで、ITが経営の変革を支える“攻めの機能”へと進化できることを実感してきました。
より具体的なCIOの仕事観、やりがいや魅力に焦点を当て、リーダーシップやITリーダーへの効果的なアドバイスなど、小和瀬氏に話を聞きました。詳細については、こちらのビデオをご覧ください。
CIOのやりがい、魅力について:
CIO、CDO、CDXOなど、呼び方は企業によってさまざまですが、私にとってCIOとは「デジタルを司る責任者」であり、経営改革・業務改革の中核を担う存在です。今やデジタルの力なくして企業の変革は語れません。だからこそ、CIOは単なるITの管理者ではなく、経営に深く関与し、業務部門とともに未来を描く“変革の推進者”であるべきだと考えています。
かつては経理・財務部門が「お金を握っている」ことで全社に影響力を持っていましたが、今はIT部門が“データ”を握ることで、経営に対して提案できる立場になっています。これはCIOという役割の大きな魅力でもあります。
しかし、日本企業は欧米のグローバル企業に比べて、IT活用の面で20〜30年遅れているのが現実です。欧米企業は1990年代後半から2000年代初頭にかけて、グローバルで業務を標準化し、データの“見える化”を実現してきました。今や、ボタン一つで全世界の経営データをリアルタイムに把握できる体制が整っています。
一方、日本企業では、いまだにグループ全体のデータが統合されておらず、海外市場での競争力を十分に発揮できていないケースが多いです。製品力があっても、”見える化”されていなければ、グローバル市場では戦えない時代に突入しています。
だからこそ、CIOの役割はますます重要となります。まずは全社のデータを”見える化”し、PDCAサイクルを高速で回せる土台をつくる。それが、これからの日本企業がグローバルで勝ち抜くための第一歩だと、私は確信しています。
リーダーシップに関して、成功するCIO(およびマネジメント層)に必要なことは何ですか?
荏原製作所の創業者・畠山一清氏が掲げた創業の精神、「熱と誠」です。それは「パッション(熱意)とデディケーション(誠心誠意)があれば、どんな困難も乗り越えられる」という信念です。この想いは、今もなお社員一人ひとりに受けつがれ、企業文化の根幹を成しています。
私自身も、CIOという肩書きに関係なく、この「熱と誠」を仕事の原動力にしてきました。一人の人間の熱意が、周囲を巻き込み、やがて組織全体を動かす力になる。そう信じて、変革の現場に立ち続けています。
もちろん、変革は一人では成し遂げられません。しかし、真摯な想いと誠実な行動は、必ず周囲に伝播し、共感を呼び、やがて大きなうねりとなって企業のカルチャーさえも変えていく。私はその力を、現場で何度も目の当たりにしてきました。
そして今、私が大切にしているのは、自分のためではなく「公(おおやけ)」のために働くという姿勢です。「会社を良くしたい、社会を良くしたい、そして日本をもっと元気にしたい」。そんな熱い想いを胸に、日々の仕事に向き合っています。
ITリーダーを目指す人たちにどのようなアドバイスをしますか?
私がITリーダーとしての視座を得たのは、30歳のときに経験した海外駐在でした。アジアの現地法人でITディレクターを任され、限られたリソースの中で経営と現場の両方を見ながら、ITを通じて課題解決に取り組む日々。振り返れば、その時に求められた役割は、今のCIOとしての仕事と本質的に変わらないものでした。
海外駐在は、単なる業務経験ではありません。日本の常識が通用しない環境で、文化や価値観の違いに直面しながら、自分の考え方や行動を根本から見直す機会でもあります。私はこの経験を通じて、「グローバルとは肌感覚で理解するもの」だと実感しました。
欧米の企業では、地方拠点での成功体験を積み重ねた人材が、やがて本社の経営層に上がっていくというキャリアパスが一般的です。これは非常に理にかなっていると思います。経営者としての視野や判断力は、現場でのリアルな経験からしか育たないからです。
だからこそ、これからITリーダーを目指す方には、ぜひ若いうちに海外での経験を積んでほしいと思います。異文化の中で自ら考え、動き、成果を出す。その経験が、将来の大きな財産となり、グローバルに通用するリーダーシップの礎になるはずです。
今後の展望、中長期的な取り組みについて:
荏原製作所では、2008年から「E-Plan」と呼ばれる3カ年の中期経営計画を軸に経営を進めてきました。しかし、2019年に策定した「E-Plan2022」では、従来の延長線ではなく、10年後のありたい姿から逆算する“バックキャスティング”のアプローチを採用し、新たに長期ビジョン「E-Vision2030」を掲げました。
このビジョンは、単なる売上や利益といった財務目標にとどまらず、社会的な価値の創出を重視しています。たとえば、「6億人に安全な水を届ける」「CO₂排出量を削減する」といった目標は、100年以上にわたり社会インフラを支えてきた荏原製作所だからこそ掲げられる、企業の存在意義を体現するものです。
この長期ビジョン「E-Vision2030」を起点に、各3カ年計画を構築し、着実に実行してきた結果、荏原製作所は4期連続で過去最高益を更新しました。
CIOとして、私はこの好調なトレンドをさらに加速させ、デジタルの力で経営改革を支え続けたいと考えています。








